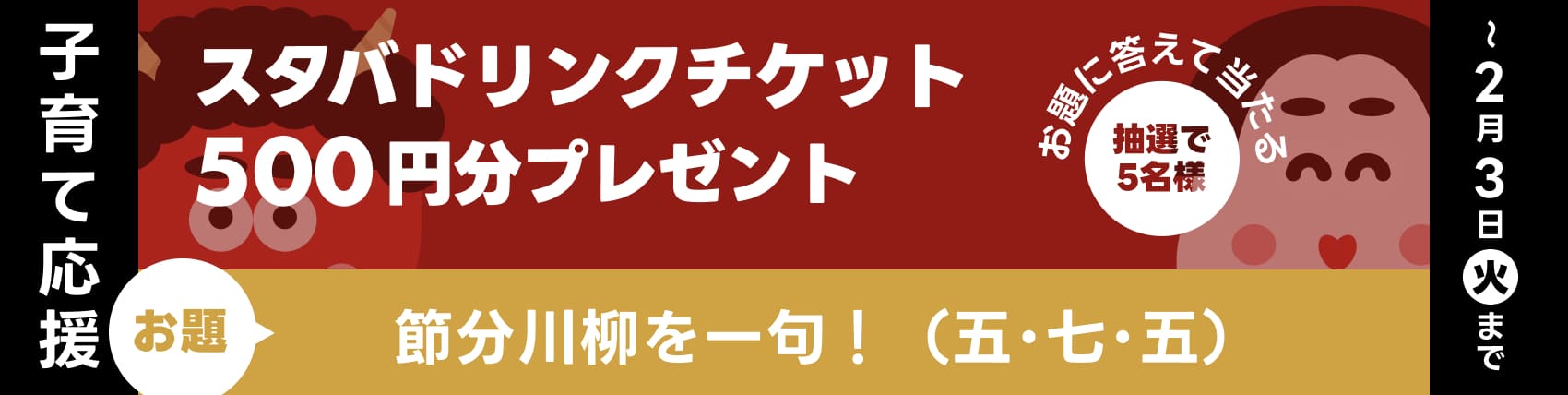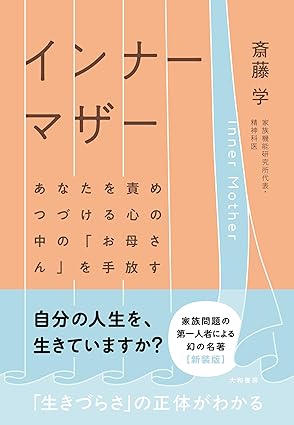「生きづらさ」の正体がわかる:インナーマザー――サバイバーとスライバー
自分の人生を、生きていますか?「生きづらさ」の正体がわかる。家族問題の第一人者による幻の名著[新装版]
親子関係

サバイバーとスライバー
サバイブ(survive)とは生き残ることです。スライブ(thrive)とは成長することです。
小児科学には、「成長の失敗(failure to thrive)」という概念があって、児童虐待などで心身の成長の停滞している子どもなどにこの用語を用います。
精神科医の私がスライブという場合は、もちろん心の成長のことです。
トラウマ(心的外傷)に関する精神療法や自助グループの分野ではサバイバーズ(生き残った人々)という言葉がよく使われます。
これはどういう人たちかというと、過去の外傷的体験、それはほとんど親による虐待などの被害を指しますが、それによって、その後の(児童虐待の場合、思春期以後の)人生が影響を受けたと考えている人のことです。
いい換えれば「今、私がこんなに生きにくいのは、親(その他の加害者)によって、あのような目にあわされたからだ」と考えるようになった人のことです。
生き残った人、サバイバーの特徴
この人たちには、いくつかの特徴があって、一つは心身の不調です。
心の障害としては、抑うつ、無気力、自殺願望、自傷行為の繰り返しなど衝動コントロールがうまくいかないこと、過食、ギャンブルなどを含む嗜癖、それに対人恐怖などがあります。
身体の不調としては、呼吸器系、消化器系の障害、生理痛や不正出血、性交疼痛などの生殖器系の障害、月経前緊張症、慢性の頭痛、思春期・成人期にまで引き続くアトピー性皮膚炎や喘息などの頻度が高い。
パニック発作と呼ばれるような、呼吸不全や心拍数増加、あるいは呼吸不全をともなう恐慌状態を頻回に起こす人々もいます。
サバイバーと呼ばれる人々は概して怒っています。
当然のことでしょうが、親への怒りがあらわで、そのことをしきりに口にします。
他人への不信感も強く、治療者に対しても怒りや不信をぶつけやすいので、扱いやすい人々ではない。
この怒りは自分自身にも向けられていますから、自己懲罰的で、自殺や自傷と結びつきやすい、といった人々です。
自己不信と著しく低い自己評価も特徴の一つとしてよいでしょう。
サバイバーとしての自己に気づくまでは、この低い自己評価が、他人への過度な迎合、従順さ、そして仕事依存的な完璧主義になっていたのです。
親を憎んでいるくせに、親とよく似た行動をとってしまうことがあるのも特徴です。
子どもを持てば親と同じように虐待する親を演じてしまう。力への渇望の強い、マッチョな男になったり、やたらに暴力で他人を支配しようとしたり、そのような男に仕える従順な女性をやっていたりします。
大人としての自分の行動の中に、子ども時代の自分が顔を出してしまうのもこの人々の特徴です。
サバイバーは、情緒的な発達に「停滞」を起こしているので、かつてのトラウマ状況によく似た状況に遭遇すると、いっぺんに子ども返り(退行)してしまう。
男の怒鳴り声、ドアの閉まる大きな音、ガラスの割れる音など、暴力を匂わせる各種の音が、そのきっかけになったりします。
ガタガタ震え出したり、逆にニコニコと不自然な笑い顔が出てきたりします。
アダルト・チルドレン(AC)という言葉はサバイバーのこうした特徴をとらえたものです。
この言葉の作り手、ジャネット・ウォイティッツは、「ACは55歳になっても、五歳のときと同じです。5歳のときの情緒と行動が、55歳になっても突然顔を出すことに気づいて、私はこの言葉をつくったのです」といっています。
非現実的な完璧を求めたり、すぐに被害妄想の虜になったりするのも、彼らがときどき子ども返りするということを念頭におけば理解できます。
子どもは非現実的なパワーの幻想に包まれ、それが壊れそうなときには被害妄想を抱きやすいものなのですから。
世の中は危険で敵対するものという思い込み
このことを一種の「時間感覚の障害」と考えてもよいでしょう。
時間感覚の障害はサバイバーの生き方のほうぼうに顔を出します。
彼らは、一週間なら一週間という単位時間の把握が、健康な人と違っているようなのです。
何もしないうちに過ぎてしまったように短く感じ、まるで浦島太郎のように「たちまちおじいさん」といった感覚に襲われやすい人たちです。
逆に、退屈で空虚な時間の群れに圧し潰されるように感じることもあります。
現在の苦痛が一生続くかのように考えて絶望してしまう人たちともいえます。
ずっと昔の心的外傷の記憶がいつまでも生々しくよみがえるという現象も時間感覚の障害といえるでしょう。
こうした時間感覚の障害は、サバイバーたちが記憶や記銘の能力に障害を生じていることによって強まります。
サバイバーは外傷体験やその周辺の記憶を忘れていることが多いのですが、思い出すのが苦痛な記憶の回想を抑制しているうちに、回想できなくなるという現象を指して「抑圧」といいます。
過去に起こった事実は思い出されないまま、そのときの不安、恐怖、絶望の感覚だけが生々しくよみがえるということになると、その生活は苦痛そのものになります。
また、サバイバーは苦痛な体験に繰り返し出合ううちに、その体験中の自分を放心状態にしておく術を会得するようになった人でもあります。
この術は、一種の自己催眠ですが、これに熟達すると体験したことが現実感を持って想起できなくなります。
中には放心したまま、はた目には異常を感じさせないので「夢の中に生きる」ようにして生きている人もいて、この放心状態を離人症とか離人症性障害といいます。
何かのきっかけで離人症が始まる場合もあり、そのときには自分の「たましい」が自分から抜け出て、自分のやっていることを外から見ているという一風変わった体験(幽体離脱)を味わうこともあります。
このようにさまざまな問題や障害がサバイバーたちにはともないやすいのですが、中でも最大の問題は、彼らに見られる世界観の歪みでしょう。
世の中を危険なもの、自分に敵対するものに満ちたものと考え、その中で自分は敗北し、絶望し、悲惨な死を遂とげるのだという思い込みです。
この非合理的な信念にそって、周囲の人々のふるまいを見れば、その人々はすべて敵に見えます。
自分を侮辱し、嘲笑し、傷つける人々の群れのように思え、どこかに逃げるか、追いつめられて反撃したくなってしまいます。
逃避して孤立している人や、攻撃してくる人に対して、世間は不審に思い、警戒します。
こうしてサバイバーの思い込みは現実になっていくのです。
家族機能研究所代表・精神科医。慶應義塾大学医学部卒業。医学博士。家族機能研究所代表。元・医療法人社団學風会さいとうクリニック理事長。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね