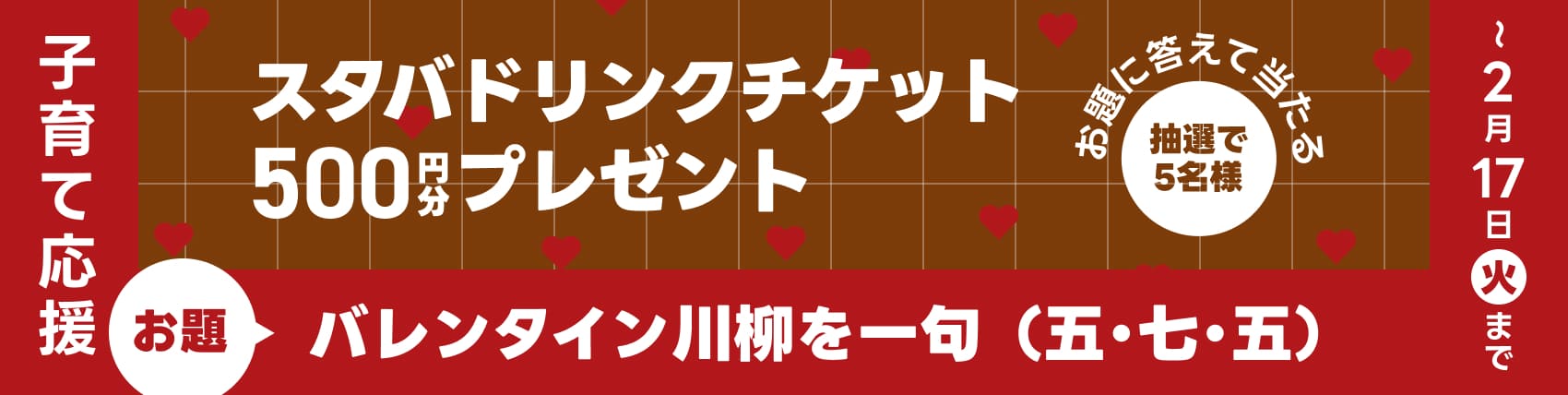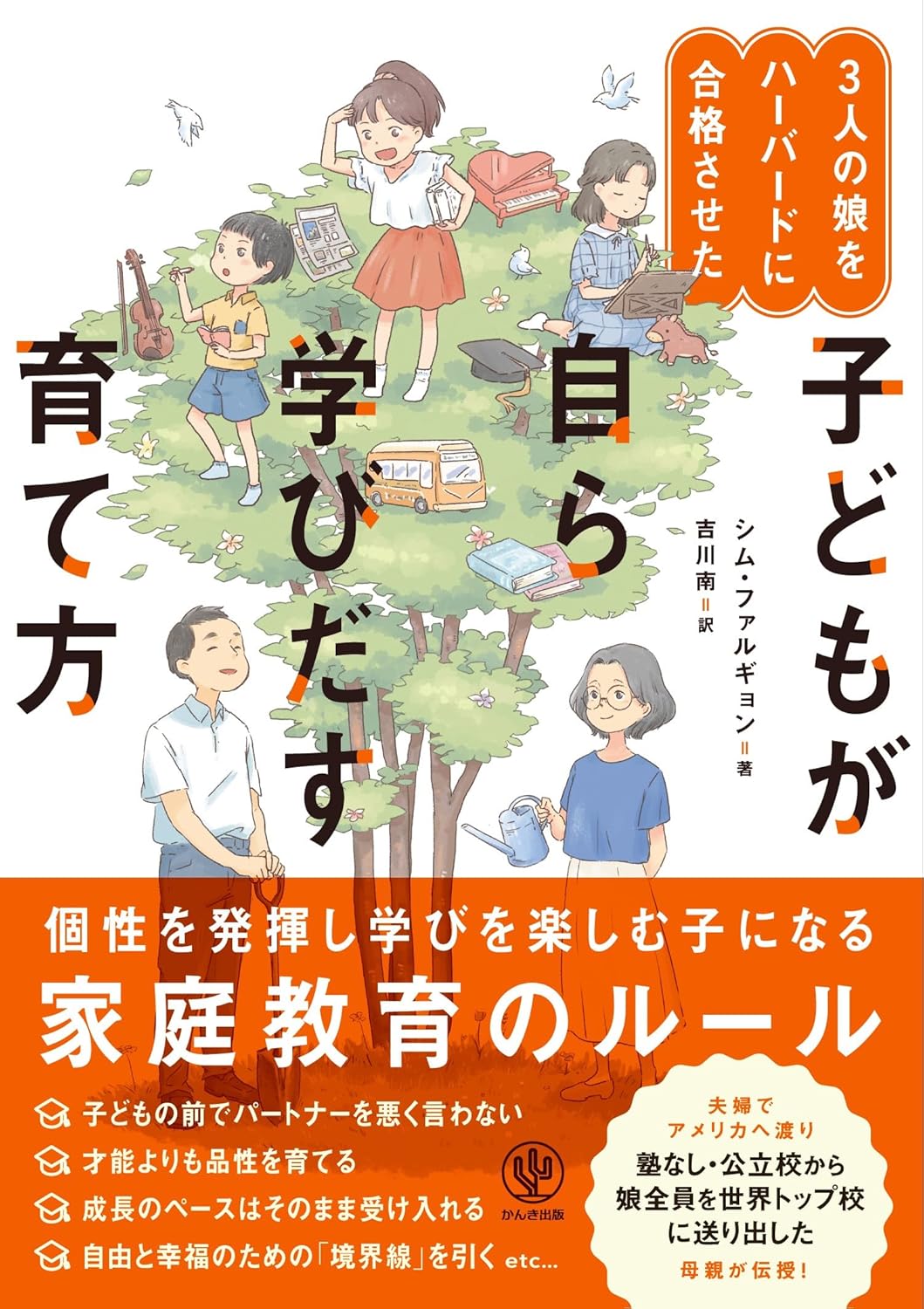自ら学びだす育て方!「権威ある親になる」
塾なし・公立校から3人の娘全員をハーバードに送り出した母親が 実際に行っていた家庭教育とは?
しつけ/育児

権威ある親になる
長女と次女が幼年期を過ごしたケンタッキー州は、美しい草原のある田舎だった。
広々した草原を、馬や牛が自由に走り回る姿がよく見られたものだ。
しかし、広大な敷地にぽつりぽつりと家が建っているのを見て、その土地にも持ち主がいることを実感した。
思う存分に自由を味わいながら、のんびりと草を食べている牛や馬も、野生ではなく誰かに飼われているのだということがわかった。
というのも、草原を区切る柵があったからだ。動物たちが安心していられるのも、飼い主が作った柵に守られているからだろう。
ある本で興味深い話を読んだ。
放牧されている乳牛と、柵のなかで飼われている乳牛の、どちらからより多くの牛乳を搾れるだろうか?
一見、放牧牛のように思われるが、実は柵のなかの乳牛のほうが、より多く牛乳を出すそうだ。
乳牛も守られて安心して過ごすと、よりよい結果が出せるのだ。
このように、子どもたちにもある程度の柵を作ってあげることが重要だ。
境界線があいまいだと、子どもたちは戸惑い、不安になってしまう。
境界線を引いてあげることは子どもを守ることであり、自分の限度に気づかせることで自ら何をすべきか、何をするべきでないかを区分する指針ができる。
親が引いた境界線のなかで、子どもたちはより幸せに成長し、より自由に大きくなれるのだ。
私は誰が何と言おうと、この点については100%の確信を持っている。
どうやって子どもを3人ともハーバードに行かせたのかと聞かれたら、子どもたちに境界線を作ってあげたからだと答えるだろう。
つまり、親として子どもが守るべきルールを作り、指針と限度を決めてあげた。
ただ、これを決めて実践するには、親の権利をどの程度まで行使すべきかという範囲も明確にしないといけない。
その範囲を定める元になるのは、親の教育哲学だ。
これが子どもの教育にどれほど重要か、そして、いつか子どもが巣立つときに、どれほど大きな影響を与えるかは、いくら強調しても足りないだろう。
子どもにはまだ柵が必要だ
幼い頃から親の愛を独占し、何のルールや制裁もなく、やりたいように育ってきた人が、社会に出てからは成功できない例を、私たちはよく見てきた。
逆に貧しい家庭環境で、親が子どもに目をかけてやれず、何の支援もないまま何でも自分で決めて育った場合も、望みの結果を成し遂げられるケースは少ない。
どうしてだろうか。
垣根のなかでうまく育つのは、守られているという安心感のおかげでもあり、親が作った枠のなかで限度を理解し、適切な態度と姿勢を学べるからだ。
ルールという垣根、限度という枠がなければ、もっと自由で、創造的で効率的な人間になりそうなものだが、絶対にそうはならない。
むしろ家庭で縛りを経験した子どもは、家を出て学校や職場などに行ったとき、自分の属する社会で望むものを手にできる人間に育つのだ。
親がある枠組みやルールを作ったとき、子どもがそれを理解してくれることもあれば、ときには理解してくれないこともある。
とにかく従順にそのルールのいい点を受け入れ、習慣として身につけ、いい結果を出すこともある。
あるいは、自分の望むものを手にするため親と交渉をしたり、親のしつけを甘受しながら、より多くのことを手に入れたりもする。
子どもはその過程で、上の世代とどう話し合うべきか、どうすれば欲しいものが手に入るのかを、自然に学んでいく。
社会のなかで望むものを得るための訓練をしているのだ。
また、コミュニケーション能力も向上するし、相手の意見を聞いて説得する技術も上達する。
つまり、このような能力は生まれつきのものと言うより、親から学ぶ後天的な能力だと言える。
では、何を基準に線を引けばいいのだろうか。明確な限度をどう決めるべきなのか。
まず、親がしっかり考えるべきだ。親としての権威を賢く使い、はっきりした線を決めよう。
そして、それを決めたら責任感を持たねばならない。
子どもの成長のために重要だからだ。
そうやって決めた基準を子どもに説明するときは、それが子どもの幸せを考えてのことであると伝えるべきだ。
他人に配慮でき、礼儀正しく、道徳的な子を育てる道のりは、決して簡単ではない。
しかし、それはすべての親ができることであり、親にとってこれほど重要でやりがいのあることはないだろう。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね