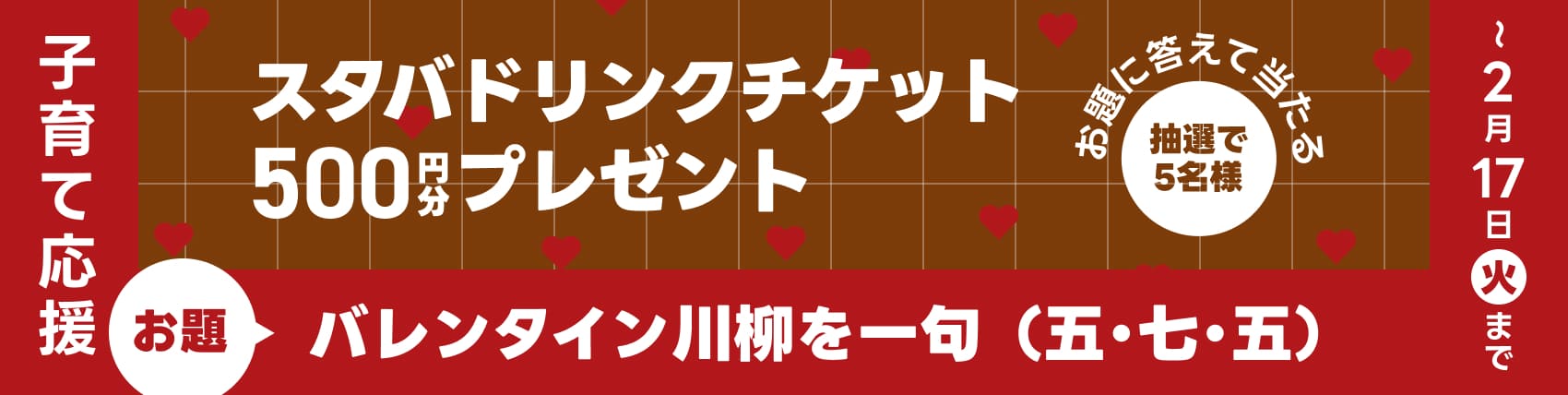「探究」はこれからの時代を生き抜くための力になる
「自ら考える人材」育成のための「探究学習」とは何かを解説。
教育

「探究」はこれからの時代を生き抜くための力になる
なぜ今、探究学習が必要なのか、
これからの時代、どのようなスキルが求められるのか
まずは、日本の教育現場に留まらず世界と未来に目を向けながら探ってみましょう
予測不可能な時代に求められる「探究する力」
今の子どもたちが大人になったとき、彼らが生きる社会はどのようになっているのでしょうか。
その答えはどこにもありません。
気候変動や食糧難、高齢化など、経済活動や社会活動に多大な影響を及ぼす問題が世界規模で深刻化しています。
グローバル化により、それらの問題が複雑に絡み合い、この先どうなっていくかは大人にも想像がつきません。
唯一わかっているのは、今は人類史すら変えてしまいかねない大きな変化が起こりうる時代であるということ、そして、これから先の予測不可能な時代を子どもたちは生き抜いていかなくてはならないということです。
古い価値観を切り替えよう
今、世界は「情報社会」といわれるSociety(ソサエティ)4.0から、Society5.0と呼ばれる「超スマート社会」に向かいつつあります。
これは、「昔とはもう時代が違う」といった数十年レベルの変化ではありません。
狩猟社会、農耕社会、工業社会と何万年にもわたって変遷してきた、人類史の大きな転換点なのです。
Society5.0は、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)VR(仮想現実)、メタバース(3次元仮想空間)などが現実と溶け合うまったく新しい社会です。
AIに使われる人、AIを使いこなす人
子どもたちは将来、AIを使いこなす人になるでしょうか?
それともAIに働かされる人になるでしょうか?
AIが進化していくと、今ある仕事の約半数がなくなる。
このような話を皆さんも耳にしたことがあると思います。
オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン教授らが、2013年に発表した論文『TheFutureofEmployment(雇用の未来)』によると、スーパーのレジ係、データ入力、銀行の窓口業務といったルーティン性の高い仕事は、AIやロボットにとって代わられるとされています。
また、2015年に発表されたオズボーン教授らと野村総合研究所の共同研究では、10~20年後には日本の労働人口の約49%が就いている職業が代替可能と予測されています。
そして実際に、その予測は現実のものとなりつつあります。
・電話を使う営業員 ・財務申告書作成者 ・モデル
・運転手、販売員 ・銀行窓口係 ・レストランの料理人
・会計士、監査人 ・不動産仲介業者 ・審判員
生き残るおもな仕事
・小学校の教師 ・看護師 ・ソーシャルワーカー
・内科医、外科医 ・作業療法士 ・弁護士
・スポーツトレーナー ・人事マネージャー ・栄養士
多くの仕事がAIで自動化されていく超スマート社会では、職種や働き方も従来とは変化します。
今は存在していない、
まったく新しい職業も多数生まれるでしょう。
AI時代に生き残る仕事は、感性や発想力、創造力、人の心を感動させる力を活かした人間にしかできない仕事です。
今後は、AIやVRなどのテクノロジーを使いこなして自ら社会をつくる人になるか、テクノロジーの変化に振り回され、言われたことだけをこなしていく人になるのかの二極化がいっそう進んでいくともいわれています。
どちらがより生き生きと、楽しく、充実感をもちながら生きていけるか。
答えは言うまでもありません。
もう、これまでのように「いい大学に入って、いい会社に就職すれば、それなりに食べていける」という「王道ルート」を求める受身の生き方では、太刀打ちできません。
変化の時代を生きる子どもたちは、どんな環境・状況に置かれようと自力で未来を切り開いていくための能力・スキルを身につける必要があります。
その土台をつくるのが「探究する力」です。
なかでも、のちほど説明する「ゼロから1をつくる力」「課題を見つけて解決策を考える力」は欠かせません。
国も教育現場も、「予測不可能な時代を生きる力」を養うべく、「探究」をベースとした新しい教育へと大きくシフトしています。
このような時代の変化を意識して子どもを育てていくことで、子どもの未来は保護者や教師の想像をはるかに超えて花開いていきます。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね