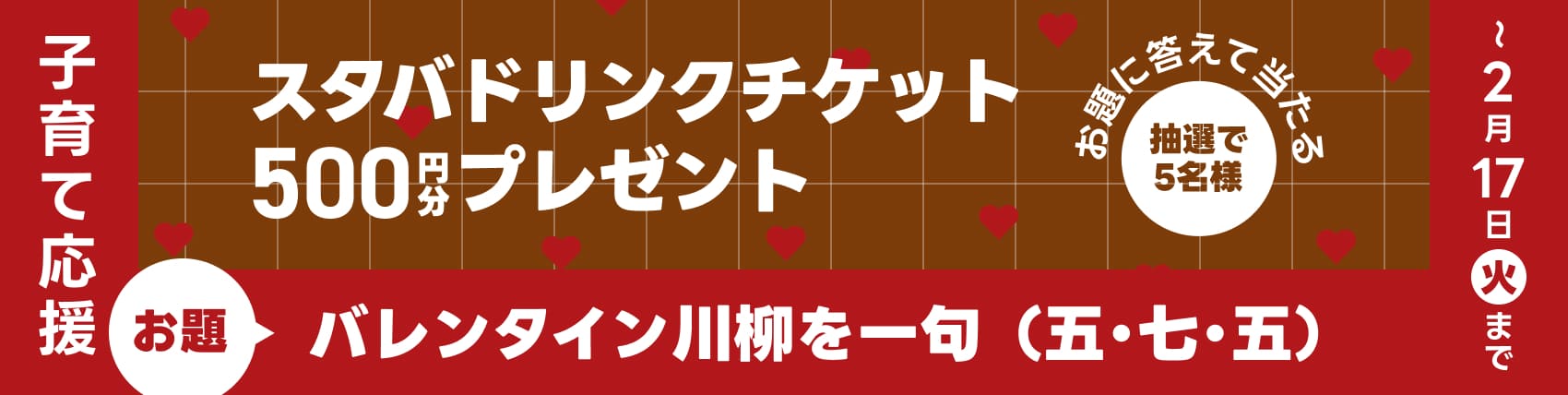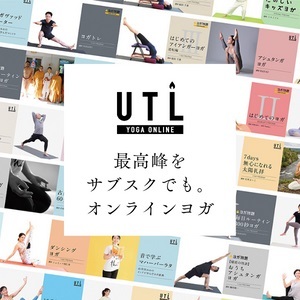大勢のママたちの問題を解決!――ぼっちママの寂しさは心の傷とつながっている
子育て特有の“孤独感″で悩んでいるぼっちママたちのために、実際に私自身も体験し、これまで大勢のママたちの問題を解決してきた方法をお伝えします。子育て中ならではの“孤独感″を知る。
人間関係

寂しさは心の傷とつながっている
では、ぼっちママたちの“寂しさ”は、一体どこから来ているのでしょうか。
私は多くのぼっちママたちのカウンセリングをしていますが、そのときに必ずしてもらうのは、それまでの思い込みをリセットして、
「本当の自分はどう思っているのか?」
ということを潜在意識の中にある
「本当の自分」
に問いかけることです。そうすると、
「本当は助けてほしかった」
「本当はあのとき、一緒に子育てのことを考えてほしかった」
といった、ママの心の内に隠れていた感情が出てくるのですね。
そして、それらの感情が湧いてくる根本原因、
「この感情は、どこから生まれたのだろう?」
ということを紐解いていくと、さまざまな心の傷に行き着きます。
けれども、今のぼっちママたちは、これまで積み重ねてきた心の傷に、絆創膏をどんどんどんどん貼って、それらの傷に蓋をしている状態です。
そうして「もう傷つきたくない」「傷つくくらいならひとりでいい」とますます孤独になるような選択をしてしまうのです。
そこで、ぼっちママたちの主な心の傷を見ていくと、次の3つが見えてきます。
①強い責任感、できないことへの罪悪感
②我慢
③幼少期の記憶
次の項目では、これらの心の傷がどうやってできたのかを見ていきましょう。
どうして心の傷は作られるの?
①強い責任感、できないことへの罪悪感
私たちは誰でも毎日の生活の中で、仕事や家事などやらなければいけないことがあり、
「これを何時までに絶対にやっておかなきゃ」
「人に迷惑をかけないためには、この仕事は完璧に仕上げるべきだ」
といった、責任感で動いていると思います。
責任感が強く完璧主義な人もいれば、「これくらいはいいか」と調節をしながらバランスを取っている人もいます。
ただ、ぼっちママの場合は、それまで「自分は責任感の強いほうだ」と自覚してこなかった人でも、子どもができたことで強い責任感が表に出てくることがあります。
「育児や家事は、私のお母さんのように完璧にするべきだ」
「子育てはマニュアル通りにやらねばならない」
「みんながやっているように、母親としてこの子を上手に育てなければならない」といった「べき」「ねば」に縛られたマイルールがどんどん作られてしまいます。
そうなると、マニュアル通りにできない子どもや旦那さんに対して、
「なんでちゃんとやらないの?」
「頑張れないならもういい」
と自分ひとりで抱え込むことになってしまいます。
それは、日本でも昔から言われている「3歳児神話」のように、
「子どもは3歳までは母親の手で育てないと、子どものその後の成長に悪影響を及ぼす」
といったことも、知らずしらずのうちにママたちのプレッシャーになっているのかもしれません。
しかも、どれだけ強い責任感があっても、子育てや家事は完璧を目指したらキリがありません。
食事を例にとっても「子どもの料理は全部手作りで」「食材にもこだわって、添加物は使わないように」「キャラ弁にして」など、やろうとしたらいくらでもできるのです。
そうなると、精神的にも肉体的にもギリギリの状態になるまで頑張っているのに、できないことばかり気になり、
「ああ、これもできてない。あれもだ……」
とさらに自分を追い込み、自分で自分の心に傷をつけ続けてしまいます。
だから、まずは、
「自分は何ができて、何はできないのか?どちらの部分も両方見てみよう」
「これって、本当に完璧にやらなきゃいけないことなのかな?いや、そもそも完璧ってなんだろう?」
「マニュアル通りじゃなくても、過去の自分と比べると、できているところもたくさんあるよね」
と思って、自分をガチガチに縛っている“強い責任感”や“できないことへの罪悪感”による心の傷を、少しずつ治していくことが重要です。
②我慢
先ほどの3歳児神話と同じように、日本には今でも、
「母親だったら、自分のことは我慢して、子どもを第一優先して当然だ」
という意識がまだまだ多く見られます。
その我慢や、自分を後回しすることの程度にもよりますが、自分の母親や義母だけでなく、助産師さん、児童館や保育園・幼稚園の先生、親戚やパートナーである旦那さんにさえそう思われていることがあります。
この本を手に取ってくれているあなたも、毎日、寝不足の中で夜中に授乳をしたり、ひとりで家事や育児をしたりと、ほとんどワンオペで頑張って、自分だけの時間どころか、食事やお風呂の時間もゆっくりとれないほど、我慢を重ねているのではないでしょうか。
その我慢が続くと、自分の心を置いてけぼりの「ぼっち」にして、自分でも気づかないうちに心の傷になっているのです。
また、幼少期の記憶にもつながることなのですが、もしかしたら無意識のうちに、
「私さえ我慢していれば、すべては丸くおさまる」
「我慢は美徳」
と考えている人もいると思います。
でも、「こんなに我慢をしているのに」「なんで私ばかり我慢しているんだろう」と少しでも感じているのであれば、もう限界まで我慢をしているのかもしれません。
「いえいえ、私は大丈夫です」
「むしろまだまだ、我慢も頑張りも足りないです」
という声も聞こえてきそうですが、実はそのように平気なフリ、大丈夫そうなフリをすることも、知らないうちに「自分の本当はギリギリ限界な気持ち」に嘘をついて、我慢につながってしまうことがあるのです。
最近の子育てに関する調査結果などを見ていても、ママたちの、「子育てのせいで(夫のせいで)我慢ばかりしている。
自分のことは後回しになっている」という声は、年々増える一方です。
働き方改革で社会の意識が変わったり、男性の育児参加は当たり前という風潮になったにもかかわらず、このような声が絶えないのは、やはりママの負担はとても大きいということです。
ママが仕事をもっている場合も、子どもが急に熱を出したときや保育園の送迎のための時短勤務で、以前のように自分らしく働けない。
そんな愚痴を言いたくても、夫はもとよりママ友とも心を全開にして話すことは難しいし、昔からの友だちには、今の状況を理解してもらえるかどうかわからないし......。となると、
「なんで私ばかり我慢をしているんだろう」
と思いながらも、我慢し続けるほうを選んでしまうのも当然かもしれませんね。
でも、子育ては今だけではありません。
子どもが成長して、大人になるまでの長い時間続きます。
強い責任感と同様に、この本を読みながら今の状況と「自分の本当の心」に向き合うことで、自分の望む子育てや夫婦の形を築いていきましょう。
③幼少期の記憶
私たちが「本当の自分」と向き合うときに切っても切れないのが幼少期の記憶です。
「幼い頃の自分はこういう子だった」
「親からよくこう言われて育った」
という自分自身の思い込みや親の口癖などは、大人になって普段意識をしなくなっても、潜在意識の中にしっかりと残っています。
そして、その幼少期の思い込みが、今のあなたの「セルフイメージ」や「マイルール」に影響を与えている場合があるのです。
セルフイメージとは、例えば、
「私は頑張らなければ役に立てない人だ」
「私のことを人は、ひとりぼっちで寂しい人と見ているだろう」
と思い込んだり、想像したりしているイメージです。
また、マイルールは、例えば、
「私は、子育てをひとりで完璧にやるべきだ」
「私は、夫に頼って迷惑をかけてはいけない」
というように決めつけているルールのこと。
これらは2つとも、私たちが気づかないうちに潜在意識の中で、思考や行動を縛っていると考えられます。
ぼっちママの場合は、幼い頃の記憶が、このセルフイメージやマイルールなどの規則となって、自分だけでなく子どもや旦那さんなど周りの人たちも縛るようになっているのですね。
ここであるぼっちママのケースを見てみましょう。
その人は「小学校低学年の子どもが自分にひどく反抗するようになってしまいました。自分もあれこれ注意しすぎてしまっているとは思っています。寂しいですけど、どうすることもできないんです」という悩みを抱えていました。
そこで、
「自分はどんな母親だと思いますか?どんなマイルールがあると思いますか?」
とセルフイメージとマイルールについて聞いてみると
と話してくれました。
「厳しすぎるママ。でも子どもは礼儀正しく育てるべきと思っています」
そして、なぜ「子どもは礼儀正しく育てるべき」と思っているのか、いつ頃からそう思ったのか詳しく聞いてみると、原因は幼少期のお母さんとの記憶にありました。
このママは、例えば小学校に入学したての頃、お母さんに外出先ではもちろんのこと、家にいる場合も、玄関で靴を脱ぐときに始まって手を洗うときも、服を着替えるときも、食事をするときもずっと、
「礼儀正しく、きちんとしなさい」
と厳しくしつけられ、監視されているような気がして、すごくイヤだったのだそうです。お母さんに厳しくされた記憶を振り返っていくうちに、
「あっ、『子どもは礼儀正しく育てるべき』というのは私のルールじゃなくて、お母さんのルールだったんだ」
ということがわかり、
「家出したいと思うほどイヤでイヤでしょうがなかったお母さんのルールだったのに、同じことを私の子どもにしていた......」
と、自分の意識の97%を占める潜在意識の中に、今の行動に影響を与えている心の傷が存在していたことに気づいたのです。
最後に私は、
「本当はお子さんとどんな状態でいたいですか?」
とたずねました。
すると、
「本当は、子どもと笑顔で過ごしたい。マイルールじゃなくて、子どもと一緒にルールを決めていきたい」
といった、本当の気持ちが出てきました。過去の心の傷に気づいて、親とは違う「本当の自分」で子育てのやり直しを始められたのです。
どうでしょうか。
みなさんも、幼少期の母親などとの関わりを思い出してみると、なんとなくそんな記憶がよみがえってきた方もいるのではないでしょうか。
幼少期の記憶をさかのぼり、自分の心の傷を自分がわかってあげることだけで、「なあんだ。これはお母さんのルールだったんだ」
と心が軽くなる人も、きっといると思います。
潜在意識にある、幼少期の記憶の中の心の傷をよみがえらせるのは、つらい過去と認識しているほど、難しいと感じる人もいるかもしれません。
けれどもそれは、心の中にいる子どもの頃のあなたが、傷ついてひとりぼっちで泣いているままになっている状態だからです。
悲しかった記憶も寂しかった経験も、大人の今のあなたが迎えに行って、話を聴いてあげることで、傷が癒やされていくのを感じると思います。
絆創膏を重ねて蓋をした心の傷を、一枚一枚丁寧に取り除いていきましょう。
――ここまでお伝えした、自分の中にある“強い責任感、できないことへの罪悪感”“我慢”“幼少期の記憶”の3つの心の傷を知ることは、みなさんが「本当の自分」を取り戻し、今の孤独感を和らげていくための、大事な糸口になります。
「私は子育てに関して、夫に心を開いて話せていなかったな」
「もうちょっと自分を大切にする時間を増やしてみよう」
「幼い頃、そういえば、お母さんとあんなことがあったな」
と、自分と向き合い、これまでの自分を認め、その心を癒やしていくことこそが、今のみなさんには必要なのですね。
公認心理師・Bigsmileカウンセラーコーチ。株式会社ビッグスマイルマザージャパン代表取締役、Big smile mamaコミュ主宰、元精神科・小児科看護師。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね