中学受験はもう古い!?「不登校・発達障害の受験戦略」
令和の受験・学歴事情を知り尽くすプロが明かす中学・高校受験の真実がここにある!
発達/発育
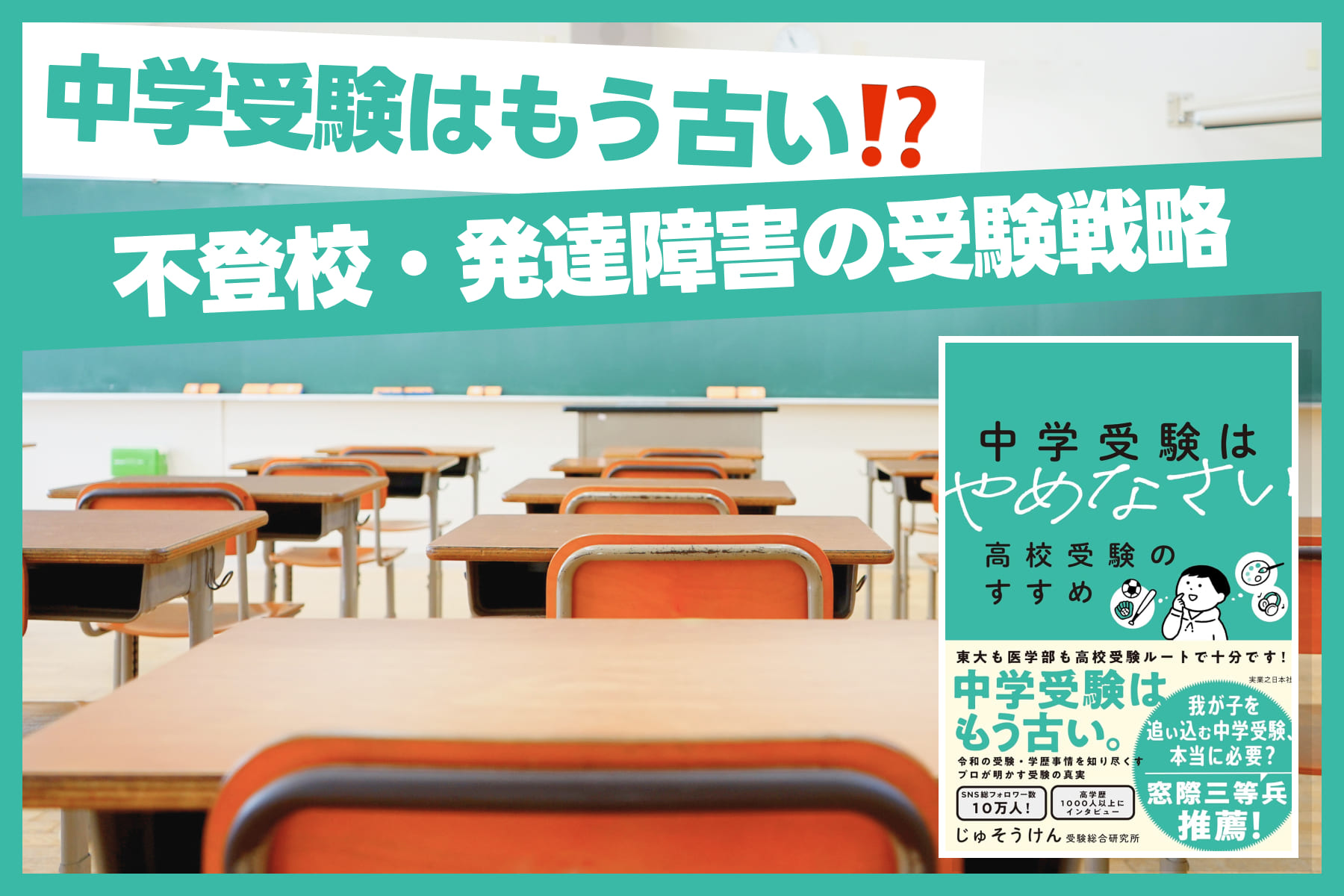
不登校・発達障害の受験戦略
近年注目を集める不登校や発達障害などの事例ですが、もし子供がこのような状況になってしまった場合、どのように受験対策をすればいいのでしょうか。
文部科学省の調査では、2022年度、不登校の小中学生が過去最高の29万9千人に達したと発表されました。これは全小学生の1.7%、全中学生の6%にあたり、2クラスに一人は不登校がいる時代となっています。
不登校になってしまう理由には、心身の不調で朝起きることができなかったり、授業のペースについていくことが困難になり登校を拒否してしまったり、いじめにより精神的に傷ついてしまったり、家庭で家族の世話や介護をしなくてはいけない事情があったり、それらの要因が複数重なっていたりと様々なようです。
不登校→本人の改善+不登校に寛容な学校
不登校になってしまった場合の対応方法は、本人の改善と、制度の攻略という2点を考える必要があるでしょう。
まず本人の改善とは、受験云々の前に、本人に心の傷などがある場合は早急にそれを取り除くような対応が必要になるということです。
無理に登校を強制すれば逆効果になりかねませんし、本人の様子や希望を見て、柔軟に対応していくことが大切です。
医師やカウンセラーへの相談が必要なのは言うまでもありません。
次に制度の攻略とは、不登校でも高校に合格できる方法を考えるということです。
特に公立高校入試の場合は、内申書や調査書が合否に直結するため、登校日数が足りなければ門前払いされかねません。
保健室への登校や、不登校専門のフリースクールに通うことで出席日数を稼ぐことができる救済制度もあるようなので、学校の先生や、自治体の相談窓口などに相談してみましょう。
また私立高校や通信制高校などでは、出席日数を重視しなかったり、不登校でも受け入れている学校があったりするため、そういった高校を狙うというのも一つの手です。
一時的に学校になじめなかった場合でも、本人の学力は高く、環境が変わればむしろ好成績を収めるといったパターンも十分考えられます。
不登校になってしまった場合は本人のケアを最優先に、受験制度も最大限攻略して新しい環境に挑戦するのがいいでしょう。
発達障害
また発達障害も近年注目を集める症例です。発達障害とは生まれつき脳機能の発達に関連した障害があることで、代表的なものに自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)があります。
自閉スペクトラム症(ASD)は、社会的コミュニケーションや対人関係の困難さや、限定された行動、興味、反復行動を特徴としており、自閉症やアスペルガー症候群、広汎性発達障害などが統合されてできた診断名です。
学校では友達とうまく交流できない、授業よりも自分の行動を優先してしまう、頑張っているように見えないので内申点が悪くなるといった問題が起こり得ます。
ASDの人は自分の世界に入り込んでしまいコミュニケーションが取れないといった難点がある一方、こだわりのある分野では天才的な成果を収める場合もあります。
注意欠如多動症(ADHD)は、不注意(集中力がない)、多動性(じっとしていられない)、衝動性(思いつくと行動してしまう)といった症状が見られる障害です。
学校では席に座っていられない、授業に集中できない、忘れ物をしてしまうといった問題行動を起こしてしまう可能性が高いです。
ADHDの人は型にはまった生活に向いていないものの、脳内多動と呼ばれる頭の回転で天才的な学業成績を収める場合もありますし、常人では思いつかない発想力を持っていたりもします。
ASD、ADHDいずれの場合も、「授業に出て、やる気のあるようにふるまう」といった内申点で重要とされる項目に向いていません。
そのため通常の中学校ではテストの点数が良くても内申点で伸び悩むといった可能性があります。
小学校の段階で勉強に適性があれば、内申点を使って高校受験しなくても済むよう中学受験をする選択肢がありますし、高校受験では内申点が重視されない私立高校を受験する選択肢があります。
発達障害の場合は環境さえ適していれば学業面で高い成果を発揮する場合もあるため、本人の適性を見極めて強みを伸ばす環境を与えてあげる必要があります。
もちろん医師やカウンセラーなど専門家に相談することが重要なので、我が子が発達障害かも?と思った段階で専門家に相談してみましょう。
受験校の選定については塾・予備校などの受験の専門家に相談することも有効です。
不登校になってしまった場合の対応方法は、本人の改善と、制度の攻略という2点を考える必要があるでしょう。
まず本人の改善とは、受験云々の前に、本人に心の傷などがある場合は早急にそれを取り除くような対応が必要になるということです。
無理に登校を強制すれば逆効果になりかねませんし、本人の様子や希望を見て、柔軟に対応していくことが大切です。医師やカウンセラーへの相談が必要なのは言うまでもありません。
次に制度の攻略とは、不登校でも高校に合格できる方法を考えるということです。
特に公立高校入試の場合は、内申書や調査書が合否に直結するため、登校日数が足りなければ門前払いされかねません。
保健室への登校や、不登校専門のフリースクールに通うことで出席日数を稼ぐことができる救済制度もあるようなので、学校の先生や、自治体の相談窓口などに相談してみましょう。
また私立高校や通信制高校などでは、出席日数を重視しなかったり、不登校でも受け入れている学校があったりするため、そういった高校を狙うというのも一つの手です。
一時的に学校になじめなかった場合でも、本人の学力は高く、環境が変わればむしろ好成績を収めるといったパターンも十分考えられます。
不登校になってしまった場合は本人のケアを最優先に、受験制度も最大限攻略して新しい環境に挑戦するのがいいでしょう。
学歴研究家。じゅそうけん合同会社代表。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね




































