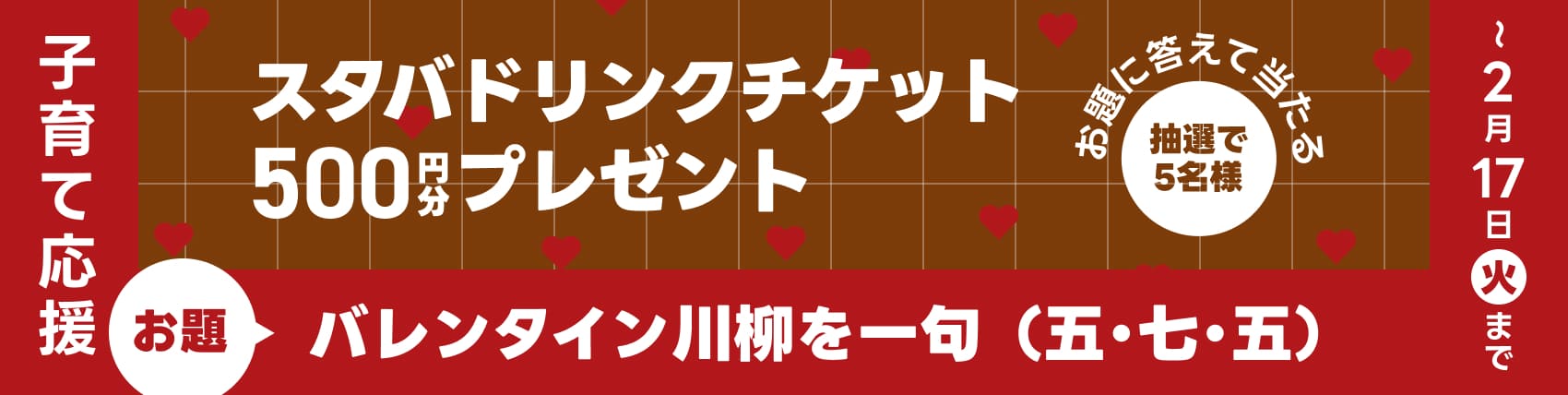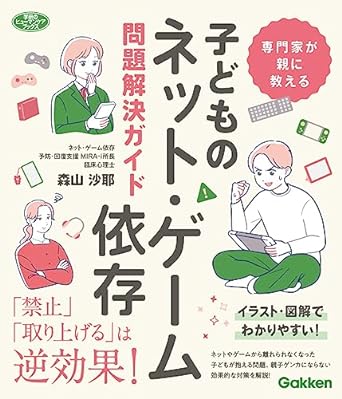専門家が教える「ネット・ゲーム以外の活動に興味を示さない時は?」
子どもがスマホやゲームをやり過ぎて、学業成績や健康面が心配、依存症ではないかと心配という親のために、予防や回復のための関わり方をわかりやすく紹介します。
しつけ/育児

ネット・ゲームは手軽に強い刺激を得ることができる
子どもにネットやゲーム以外にも「何かやったら?」と聞くと、子どもは「他にやることがない」と言う、「じゃあ、これやってみたら?」と提案するも断られる、やっても続かない、すぐに飽きてしまう......こんな経験はないでしょうか。
動画やSNS、ゲームはいつでもどこでもその場にいながら手軽に楽しい刺激を得ることができ、しかも、飽きずに続けられます。
一方、現実の遊びや余暇活動は、移動しなければできない、道具を準備する必要がある、知らない人とのやりとりがある、など子どもによっては取り組むハードルが高いことがあります。
その結果、ネットやゲーム以外の活動のレパートリーが広がりづらくなってしまうのです。
促すときのよくある失敗
勉強、読書、家事のお手伝いなど、親のしてほしいことを子どもに提案してしまうことがよくありますが、こうした提案は、子どもがしたくないと思っている場合に受け入れられないばかりか、反発すらされてしまいます。
また、子どもが楽しめるだろうと考えていたとしても、ずっと家にいる子どもにキャンプや登山を提案しても、ハードルが高すぎるかもしれません。
このように、親の提案と子どもにとって楽しいと感じることにズレがあるときは、うまくいきづらいのです。
子どもがハマっているネット・ゲームにヒントがある
まず試してほしいことは、子どもがネット・ゲームの何に魅力を感じているのかを探ることです。
ネットやゲームといっても、具体的に何にハマっているかは、それぞれの子どもによって異なります。
例えば、シューティングゲームであれば、スリルや興奮、チームでの達成感などを魅力に感じているのかもしれません。
一方、サンドボックス系のゲームでは、プレイヤーが自由に目標や目的を決めて遊びます。
こういったゲームでは、創造性が刺激されることや、自分の作品ができたときには達成感を得たりするでしょう。
動画についても、ゲーム実況、お笑い、アニメなど種類によって楽しさは異なります。
さらに視聴だけでなく、自分で動画を編集したり、配信していたりする場合もあります。
SNSでは、オンラインでのコミュニケーションに楽しみを感じる人もいれば、「いいね」されるなど承認されることで満たされた気分になる人もいます。
このように子どもがハマっているネットやゲームを具体的に把握することで、子どもがどのようなことに楽しみや喜びを見いだすのかを理解することができます。
子どもの興味に合わせて活動を選ぶ
ポイントは4つあります。
●子ども本人が楽しいと感じられる活動
●時間や果たす役割がネット使用と拮抗する活動
●今もすでにしている活動(もしくは将来的に起こりうる活動)
●家族も一緒に参加して楽しむことができる活動
シューティングゲームが好きな場合は、スリルや爽快感を得られるような活動がよいかもしれません。
例えば、ボードゲームやトランプであれば上記の要素を満たせるルールのものをチョイスする、運動であればジョギングよりも対戦型のスポーツのほうがより楽しめるでしょう。
時間や果たす役割が拮抗しているというのは、通常ゲームをしている時間を別の活動に置き換えてみる、ゲームと同じように楽しい気分・達成感を得られる別の活動に置き換えてみるということです。
例えば、朝起きてすぐに育成シミュレーション系のゲームを始める代わりに、朝起きてから植物の世話をすることを習慣にしてみる、などです。
促し方、誘い方のコツ
まずは、小さい一歩から始めるのがコツです。
遠くに出かけるのが難しい場合は、近くの公園にするなどハードルを下げる工夫を考えます。
そして、好きな人と一緒に行く、好きな食べ物もセットにするなど、好きなものを組み合わせることでさらに魅力が高まります。
ネット・ゲーム依存症専門の予防・回復支援サービスMIRA-i(ミライ)所長。公認心理師、臨床心理士、社会福祉士。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね