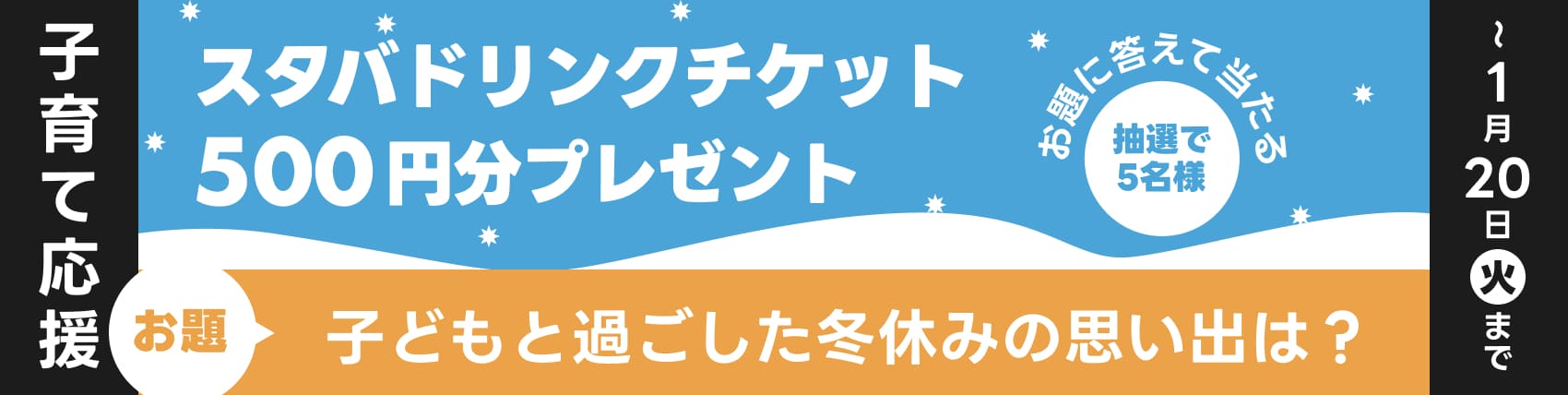子どもが勝手に自宅学習する!「 博物館や学校説明会の利用方法」
8人きょうだい長男が、 通塾なしで開成中学に逆転合格! 偏差値40台からの最難関突破法とは? 人気ブログの全貌を初公開!
教育

Q.博物館や実験教室などの実体験はしましたか?
「教科書で勉強するのと、現地で体験するのは全然違います。できる限り、親子で色々なところへお出かけしました」なんていう体験記を読むと、すごいなあと思います。
オトクサ家の場合、旅費も時間もなく、これといった実体験はしていませんでした。
前述した知育教育や過去問の2周目と同様に、実体験は「やらないよりやった方がいい」という考えです。
博物館や実験教室などの実体験は、確かに子どもの知識や経験につながるでしょう。
ただ、そんな余裕があるご家庭は一握りなのではないでしょうか。
私は、現場で見たり聞いたりする以上に、それについて親子で会話をすることが重要だと考えています。
極端に言えば、YouTubeでも、図書館にある図鑑でもいい、親子で一緒に見て会話できれば十分なのではないでしょうか。
実際にオトクサ家で行った工夫をご紹介します。
小学6年生になる前の春休みに、オトクサと長男で「1日図書館デー」を作りました。
目的は、ビジュアルでわかりやすい理科の図鑑や参考書を読み漁ることです。
単元をひと通り終えて、問題集でさまざまな出題パターンを味わったこの時期だからこそ、あえて理科を視覚で振り返る機会を設けました。
オトクサ家の1日図書館デー
1.受験と関連しそうな図鑑をピックアップ
●中学受験向けの本ではなく、春の植物だけで1冊、台風だけで1冊あるような専門的な図鑑
2.どんどん机に積み上げ、長男は写真を中心にインプット
3.オトクサは読み終わった本を随時返却しながら、新しく図鑑をピックアップ
4.合間に長男と一緒に図鑑を読みながら会話
6年生になる前の貴重な1日でしたが、長男にとっては良い息抜きとなり、プランを立てた時から楽しみにしていました。
「すごいね、この断層」「昆虫の口って全部違うんだねぇ」といった会話をしながら、楽しく1日を過ごした記憶があります。
中学受験に適した図鑑で、出題可能性がある写真が網羅され、丁寧な解説も記載されているためおすすめです。
次男はこの図鑑を使用して勉強していますが、あえて図書館に行って図鑑を見ながら会話する1日も作りたいと考えています。
Q.学校見学会や文化祭等には参加しましたか?
オトクサ家では、小学5年生の時に開成中学校の説明会に参加しましたが、それ以外は何も参加していません。
学校が開催する説明会や文化祭への参加は、各家庭それぞれの判断だと考えています。
実際に足を運べば子どものやる気スイッチにつながりますし、保護者の新しい発見にもなるので、まったく否定はしません。
実際、オトクサ家の三男は、長男が運動会で出場した「馬上鉢巻取り」に憧れ、開成中学校を受験したいと言っています。
しかし、受験する可能性があるからと闇雲に説明会に参加するのではなく、何を聞くのか、何が判断基準なのかを明確にして参加することが大切です。
判断基準を持たないまま漠然と参加すると、どの学校も素晴らしく見えてしまう傾向があります。
よく学校の先生や生徒の印象の良し悪しが話題になりますが、それは偶然の要素が大きいと割り切った方がいいでしょう。
もちろん学校としての大きな傾向はありますが、どの学校にも子どもに合う・合わない先生や同級生がいるものです。
「雰囲気がいい!」「インスピレーション!」といった感想は、実際に通う子どもが感じ取るならいいのですが、親が感じる「何となくいい」という印象は意味がないと考えています。
わが家の判断基準はとにかく「学校へ通いやすいかどうか」です。
通学時間が短いに越したことはありませんが、たとえば乗り換えて5駅なら、乗り換えずに10駅の学校の方が優先度が高くなります。
実際に通う可能性があると考えていた渋谷教育学園渋谷中学校には、平日の通学時間に長男と一緒に行ってみて、通学がつらくないかの確認をしました。
三男は開成中学校の運動会で心を動かされたため、兄と同じ学校を目標にしていますが、今のままでは到底届きません。
2年後に心置きなくチャレンジできるように、受験日が2月1日以外で、通いやすい中学校のピックアップをしているところです。
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね