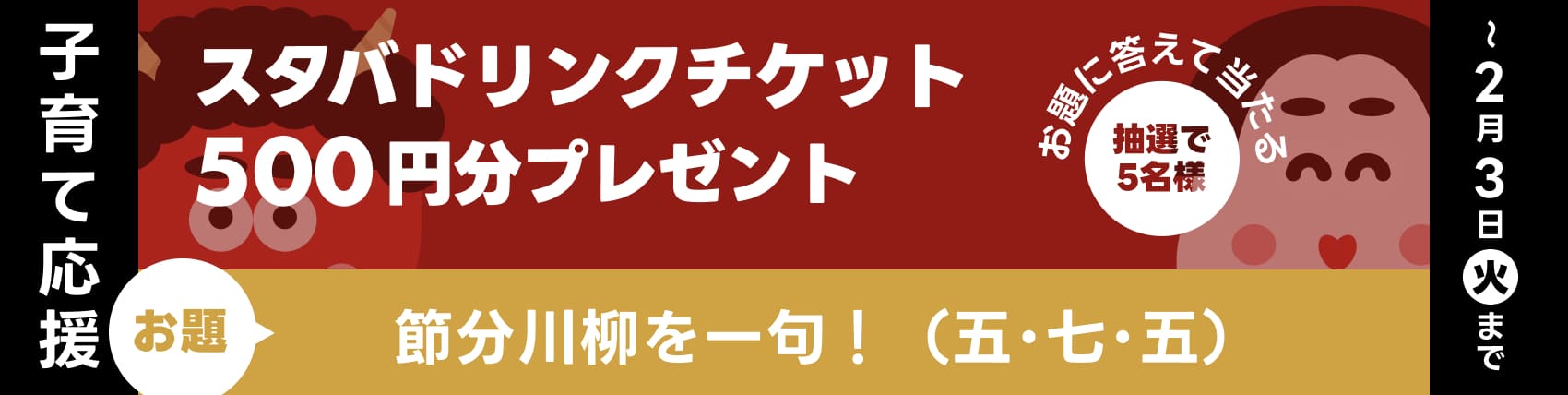正しい読書のハマり方“「レベル」と「好み」を見極める”
1日2時間の動画が、1日2冊の読書になる! 1万人以上の子どもを読書にハマらせた著者だからこそ伝えられる、家庭でできる読書教育のコツ
教育

「レベル」と「好み」を 見極める
子どもが読書を好きになれるかどうか。
それは、本選びにかかっているといっても過言ではありません。
読書家への扉はいつでも、お気に入りの1冊との出会いによって開かれるからです。
難しそうと思いつつも読みはじめてみたら、意外と楽しく読破できて、「ぼくもやればできるんだ!」と達成感を味わえた。
たまたま読んだ本の中に自分が大好きな世界が広がっていて「本ってこんなにおもしろいんだ! それならもっと読んでみたい!」とワクワクした。
そんな経験をすると、遠くに感じていた本の存在がぐっと身近なものになります。
本の内側には、まだ知らないワクワクするような世界が広がっている。
そして自分は、その世界に入りこんで味わうのに十分な力を持っている。そんな実感を持てたなら、本への関心はどんどん高まっていくはずです。
では、そうした1冊に出会うためには、一体どうすればいいのでしょうか。
そこで手がかりになるのが「レベル」と「好み」という2つの軸です。
「レベル」も「好み」も、子どもに合ったものを選ぶことが重要です。
●レベル
子どもは日々成長していきます。
そのため、成長の段階にぴったりフィットする本を選ぶことが非常に重要です。
たとえば、習っていない漢字や知らない難しい言葉にぶつかると、とたんに難しく感じるから。
特に、読書に慣れていない子どもにとって、本はそもそもハードルの高いものです。
加えて、背伸びしないと読めないような難しい本であれば、すぐに閉じたくなってしまいます。
また、オチの部分にわからない言葉があったためにオチが理解できず、好みに合っているはずの本なのにとてもつまらなく感じてしまうこともあります。
レベルが合わない本を読むことで難しさやつまらなさを感じ、子どもは読書嫌いになってしまうのです。
●好み
子どもには、一人ひとり好みがあります。
その好みにぴったりと合う本に巡りあえば、読書のおもしろさに目覚める可能性は高まります。
本のジャンルがファンタジーなのか、学園ものなのか。
登場人物の性格が好奇心旺盛なのか、クールなのか…。
そうした特色が読者の好みに合っているかどうかは、読後の満足度に大いに影響を与えます。
同じ本を読んだところで、子どもによって感じ方が違うのは当然のこと。
人気の本だからといって、すべての子どもの心に響くわけではありません。
好みを意識して本を選んだほうが、楽しさを感じやすくなるのです。
そこで必要となる読書教育は、子どもの「レベル」と「好み」を見極めるお手伝いをすること。
そうして子どもとの相性がぴったりな本と出会えるようにすれば、読書家の扉は開きやすくなるのです。
「つまみ食い読書」で5分ずつ読む
たとえば自分に合う服を買いたいと思ったとき、気になったいくつかの服をお店で試着してみる人は少なくないはず。
そうして感触を確かめるプロセスを経ることで、より満足度の高い選択ができるようになるからです。
子どもの本選びにおいても、同じことがいえます。
まずはいろいろな本を少しずつ試してみましょう。
思いのままに、本の「つまみ食い」をしてみるのです。
具体的な方法としては、子どもとともに図書館の本棚を巡り、できるだけジャンルがバラけるように本を5〜6冊ほど選んでみてください。
もしも子どもが自ら「おもしろそう」「読んでみたい」と選んだ本があれば、それがどんな内容のものであっても口出しせずに候補に入れておきます。
そうして本を選んだら、机の上に広げて、冒頭の部分だけを読んでみます。
5分ほど読んだら次の本へ。
また5分読んだら次の本へ。
そうして複数の本を、つまみ食いをするように読んでみるのです。
そうするうちに、
「乗りものがたくさん登場する本よりも、動物が主人公の本のほうが好きかも」
「文字が多い本よりも絵本のほうが自分に合っているかも」
というようなその子ども特有の傾向が、少しずつ見えてきます。
あとは「続きを読んでみたい」と思った本だけを読めばOKです。
つまみ食い読書をしていくと、今の子どもに合う本が少しずつ浮き彫りになっていきます。
大切なのは、とにかくたくさんの本に触れてみること。
いろいろな本に触れるなかで「好き」と「これではない」を実感しながら、絞り込んでいきましょう。
そうしてトライ&エラーを繰り返しながら探していけば、いつか必ず心に響く本と出会えるのです。
Yondemy代表取締役
※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
※Amazonのアソシエイトとして、てつなぎは適格販売により収入を得ています。
記事の内容がよかったら「イイね!」ボタンを押してね